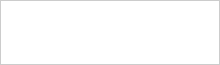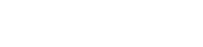株式会社タニサケの元会長松岡 浩さんは、いつも語っていました。下座行の大切さを知ることだよと。自分の立場をいつも下座に置くことにより、階段を一歩ずつ登っていける。するといつのまにか、誰も行けない場所からあらゆる景色を見渡すことができる。経営者だけでなく、人として大切な心構えであると。実際にタニサケ様の企業理念は「先も立ち、我も立つ」で、「人を喜ばせた後自分も喜ぶ」ということです。では、何故下座に立つと登って行けるのでしょうか?
登っていくという行為には、「進むが良いか退くが良いか」の判断を常にしていくことがあります。どうやら必ずしも進むのが良いとは限らないことも多いです。進み方次第では形の上では大いに進んでいるように見えても、その実かえって退いていることがあり、その反対に一見いかにも退いているように見えて、実は大いに進んでいる場合もあります。人の生活の場で例えるならば、退くことの好きな人ほど、かえって共同の仕事の推進力となり、進むことの好きな人ほど、かえってその邪魔になるということが、よくあるものです。このような事例から進むのが良いや退くのが良いといっただけでは、訳がわからなくなります。何が本当に進むことであり、何が退くことなのでしょうか?
どうやら「公共のために自分を生かすのが、本当の意味で進むことであり、その反対に自分の立身出世のことばかり考えるのが退くこと」と考えたらよいようです。公共のために生きるのは、第一に謙遜であるべきだと思います。謙遜な人ほどよく人に功を譲ります。形の上ではいつも退いてばかりいるように見えますが、その実共同生活の全体を押し進めている人なので、本当の意味で進んでいる人です。
中江藤樹の言葉があります。「人は生まれた瞬間から、人に勝ち、人の上に立ちたいという気持ちをもっています。その癖、そういった資格を備えるようになったのは極めてまれです。それはなぜかというと、人に譲り、人の下に立つことを学ぼうとしないからです。人の上に立つものは、必ずまず、人の下に立つことを学ばねばなりません。それも将来、人の上に立つことを目当てにして、その手段として人の下に立つことを学んだのでは何の役にも立ちません。それでは決して人の下に立つ道は会得されないのであります。純一無雑になって喜んで人の指図をうけ、心むなしくして人に教えを乞い、一生それで終わっても悔いないだけの慎ましさがあって、初めてそれは会得されるのであります。そして、それでこそ自然に人に推され、人の上に立つだけの資格ができるのであります。よく下るものはよく学び、よく学ぶものはよく進む。これが学問の法則でもあり、また処世の法則でもあります」と。
下座に立つと自我を超えて、全体がどうあるべきかについて考えだします。下座に立つとは、社会公共のために生きる心の出発点なのです。
合掌
SEIWAKASEI Co.,ltd
お気軽にお問い合わせください
TEL 0562-47-6101
MENU
お知らせ