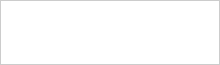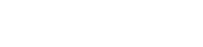森信三哲学の弟子の寺田一清さんの下座行についての言葉です。
「昨今は、自己アピール全盛の時代だ。自分を知って貰わねば、不当に評価され冷や飯を食わされる。と自分を必要以上に大きく見せる人も多い。それとは真逆な考え方が、この下座行だ。どんなに低く見られようと、それを微塵も不満に思わず、淡々と仕事をこなし、生活する。人よりも一段と低い位置に身を置き、不平不満を表さないことは、己を磨く修練であり修行だ。人は一生のうちには、何度か高慢になるときがある。現在成功しているいないに関わらず、自分よりうまくいっていない人、もっと下にいる人を見ると、見下したり高慢になったりする。なまじ学歴や、才能が自分にあると思っている人は、この罠に陥りやすい。自分の高慢な心を打ち砕く「下座行」は、年を重ねれば重ねるほど必要となる。
次に父磯野俊雄から聞いた下座行の言葉です。
「商人はすべからく頭を下げよ。先に頭を下げた人が勝者だ。人より先に頭を下げられたら、しまったと思え」「写真に写るときに、率先して中央に行く奴はダメな奴と思え」「会社に来る人々は全て福の神である。全ての来る人に暖かい言葉をかけよ」
次に江戸しぐさからもこの下座行は学ぶことができます。
① 江戸の「お早う」言葉
「おはよう」の挨拶は、これから始まる一日はどんなことがあるかわからない時点で朝早くの真っさらな自分の心の状態を伝え、「あなたにとっていい一日であるように」と願う言葉だった。
② 「あとひきしぐさ」
客を送り出す際に、姿が見えなくなるまで見送る。相手の心に余韻が残ってもう一度話をしてみたいという名残惜しい気持ちになっていただくような心遣い。
③ 「草主人従そうしゅじんじゅう」
自然が主で人間が従という宇宙観を持ち、人間は謙虚さを欠いてはいけないという教えです。
最後にノーベル賞受賞者の天野浩教授の逸話です。
ノーベル賞の候補に挙がって10回目で受賞したが、当日は名古屋大学に黙って海外に雄飛していた。着いた飛行場で取材の人ごみを見て有名人が来ているのだと思ったら自分のことで驚いた。日本では本人がいなくて大騒ぎとなり、本人不在の祝う会となった。メールを見たらノーベル委員会から1週間以内に連絡を寄こさないと受賞を取り消すと連絡があり、慌てた。
自分の成功については多く語らず、苦労話やこのエピソードを面白く語る教授でした。
下座行は自分もまだまだ足らないし、永遠に考え自分の日常に落としていくテーマです。
発がん抑制などに寄与するYAP(親切遺伝子)は、下座行を意識することで、活発に活動するのかも知れません。
合掌
SEIWAKASEI Co.,ltd
お気軽にお問い合わせください
TEL 0562-47-6101
MENU
お知らせ