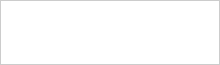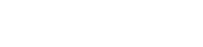鍵山秀三郎さんは言わずと知れた掃除の神様です。当たり前にやる掃除を徹底的に磨き上げる中で、掃除のやり方と自分の心を磨く方法を確立されて、掃除道として、「掃除に学ぶ会」「日本を美しくする会」を立ち上げました。脳梗塞で倒れ、今年1月2日に逝去されるまで、ひたすらに掃除の実践を重ねてその功徳により、掃除の運動は全世界に広まり、人を育て、環境を良くしています。
鍵山さんとの個人的な思い出があります。10年程前に、タニサケの松岡会長が音頭を取り、「新宿掃除を学ぶ会」の前に、鍵山さんを囲んで5名でお蕎麦をいただきました。初めてお会いし、名刺を交わしたときに、直立不動の姿勢と暖かい眼差しがとても印象的だったのを思い出します。翌日は新宿で早朝から200人程度で掃除をしたのですが、鍵山さんが、下水道に繋がる側道のグレーチングを外して、這いつくばって掃除しているのを見たときは、ここまでやるのかと驚きを禁じ得ませんでした。「凡事徹底」とは、こういうことなのだと思ったものです。鍵山さんの講演では、自分の体験から染み出した独特の珠玉の言葉がありました。生涯の信条は「人の心をすさませない」で、すさんだ心の集団・会社ほど悲惨なものはないと述べています。その他多くの語録を残しています。
①微差の積み重ねが大差になり、絶対差になる。
②(人でも物でも)いま、手もとにあるものの価値を生かす。
③世の中では死ぬか生きるかというような修羅場を潜ると、大抵の人はしたたかな人、あるいは心のすさんだ人になりがちです。
俺はこんな修羅場を潜ってきたから怖いものはないんだという人間になってはいけない。どんな苦しい体験をしてきても、いつも純粋で柔軟な心を持って、瞳が澄んでいるような生き方をしたい。
④できるだけ手を抜いて、小さな努力で大きな成果を得ようとする人は、一時はよくても必ず行き詰まる。
⑤「益はなくても意味はある」自分の利益に結び付かないことでも、周囲の人や社会・国家のために努力すること。それ自体に大きな意味がある。
⑥人間の幸福は、自由の中に存在するのではなく、義務の甘受(快諾するという意味に使われた。今とは異なったニュアンス)の中に存在する。
⑦我を捨てて人に尽くしている人の存在感はどんどん大きくなってくる。逆に、お世話になる立場から抜け出せない人は、どんどんしぼんでいく。
⑧やらなければならないことだけをやっているようではだめ。本来、やる必要のないことをどれだけできるか。それが人間の魅力をつくる。
掃除を徹底すると、いろいろなことが見えてくるのでしょう。鍵山氏の言葉を自分のこととして実感できるようになりたいですね。
合掌
SEIWAKASEI Co.,ltd
お気軽にお問い合わせください
TEL 0562-47-6101
MENU
お知らせ